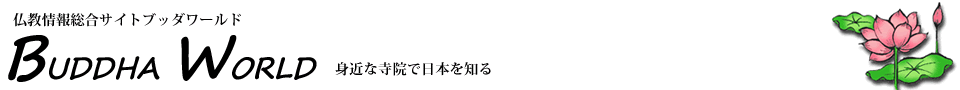
|
■葬送儀礼について
葬送の「葬」という字は、死を上下でおおうと書く。この文字通りに葬とは、死を隠して見えなくすることである。死は死体と死霊とに大別されるため葬送儀礼も死体処理と死霊の鎮魂とに大別され、合わせて死者を葬る一連の儀礼を葬送儀礼と呼ぶ。 葬儀の形式は、基本的な意味では生者と死者との分離が主要なモチーフとなって構成されるが、死者の霊に対する生者の受け止めかた、すなわち民族のもつ霊魂観、他生観により儀礼の形式もまた変遷してきたといえよう。生者が死者に対して抱く感情とは、死者に対する愛惜の情と屍体に対する恐怖感、嫌悪感とが錯綜したものである。この相矛盾した情緒を静め、均衡関係に保つために、さまざまな葬法が生み出されたともいえるのである。 『釈氏要覧』(1019年・栄道誠集)には葬法の頃に「天竺には四あり。一には水葬、謂くこれを江河に投げ以て魚贅の飼となす。二には火葬、謂く薪を積んでこれを焚く。三には土葬、謂く岸傍に埋めて速朽を取る。四には林葬、謂く寒林に露置して、諸の禽獣の飼となす」と書かれており、古くからインドには水葬、火葬、土葬、林葬の四葬が行われていたことは明らかである。 わが国の葬送の記述として『魏志倭人伝』には「其の死には棺あるも槨無く、土を封じて家を作る。始め死するや停喪十余日、時に当りて肉を食わず、喪主哭泣し、他人を就いて歌舞飲酒す。巳に葬れば挙家水中に詣りて澡浴し、以て練沐の如くす」とある。死者の甦りの場でもあり鎮魂の場でもあった喪屋がつくられた記録は『日本書紀』に「疾風を遣して、尸(かばね)を挙げ、天に致さしめ、喪屋を造りて殯(もかり)しき」と書かれている。死体への恐怖・嫌悪感と愛惜の情という相反する感情の併存、他界観などさまざまなからみ合いを知ることができる。 わが国が伝統的に伝えてきた敬神の習俗である神道においては、死者を忌む風習が強く、厳粛な死の問題と直面することを避忌し、奈良朝以降、死者のための葬儀は、もっぱら仏教の手に委ねた。そのため神葬祭の歴史は浅く、二、三の藩を除いては、ほとんどが明治維新以後のことである。現存する葬送習俗は、仏教と在来の素朴な他界観の習合によってその形式をつくり上げているといえよう。 釈尊はもっぱら死を超越し、覚者となるための真実の道を拓いたのであり、霊魂の有無、滅不滅といった形而上の問題を説いてはいない。それらは釈尊を慕う弟子の心情から発したもので部派仏教以降の展開なのである。釈尊は父王を荼毘に付し、その遺骨を金匱におさめ、塔を建てて供養し、釈尊自身の入滅には、その遺体もまた荼毘に付して遺骨を分配し、各国に仏舎利が建てられた。その後も後秦の鳩摩羅什、宋代求那跋摩等の訳経者が火葬されることにより、僧俗の間に行われるようになり、ついに火葬と土葬の二種が日本の葬法となった。わが国の葬法は古代においては死体遺棄か土葬であり、仏教の伝来とともに火葬が行われるようになったのである。ちなみに、わが国の仏葬の起源は、天平勝宝8(756)年聖武天皇崩御の際、焼香、憧幡、華鬘等の仏器を用いて葬られたというのが初見である。 葬儀を「死出の旅立ち」とする概念は、日本ではかなり古くからあったが、特に浄土教が盛んになるに至り、死者はこの世から十万億土の浄土へ旅立つものとされ、棺のなかには笠や杖、金や食料としての米などを入れ、死者にもわらじをはかせ経帷子を着せて旅姿をさせる風習が一般化した。仏教葬儀の中心である「引導」は、死出の旅路を迷うことなく辿れるためのものであり、その際導師の振る「下矩(あこ)」は、冥界の闇を照らす光である。浄土真宗、日蓮宗を除き、葬儀式の前に死者に授戒を施し、仏者として旅立たせるのも、旅路の安泰を願ってである。 |